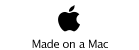12月には、クリスマス
仕組まれた苺
自分でもどうしてあんな大胆なことを言ったのか…、実は良く分からない。
私は1月18日生まれ。
今日は12月24日。
一ヶ月………ない。
私が、その、あの、あれをするまで。
自分でも、10月より、11月より、今、そして12月1日よりも、2日よりも、今日の方が脇田君のことを好きなのが分かる。
本当は恥ずかしいけど、脇田君と何回もキスをした。それどころか、胸に直接キスされたり、服の上から色々なところを触られたりもしている。
最初は驚いた、っていうか、このまま心臓が止まったらどうしようと思った。でも、今では、何ていう言葉で表したらいいのかよく分からないけど、『知りたい』。
何を、知りたいの?、私は…
「お待たせ。」
「ううん、10分も待ってないよ。」
私の言葉を聞いて、脇田君が声を殺して笑ってる。
「何が可笑しいの?」
「別に。ただ、こういう時って、そんなに待ってないとかなんだとか言うのが普通だから。だから面白いと思って。」
「ふーん、そうなんだ。」
良く分からないけど、普通じゃないのが面白いんだ。
「あ、荷物かして。持つから。」
「いいよ、いいよ。」
「そんなわけにはいかないよ。」
大した荷物じゃないけど、脇田君が当然のように持ってくれる。
なんか照れくさい。
脇田君の家へ行くときは、いつも脇田君が駅まで迎えに来てくれる。本当の事を言うと、もう脇田君の家までの道のりは覚えた。本人にも伝えたけれど、何故か迎えに来てくれる。
ちなみに脇田君の家は大きな家が並ぶ住宅街の中にあって、どこの家もお庭が広い。いわゆる高級住宅街。
そのせいか、クリスマスの今は玄関に品の良いリースとか、自前の木に飾りがついてたりする。
クリスマスパーティー、なんかこの言葉もこの地域にはしっくり。
「いらっしゃい。」
玄関では脇田母とマロンちゃんがお出迎えをしてくれた。
脇田母は今まで見たどの脇田母よりも楽しそう。どうしてだろ?
「ひとまず荷物は要の部屋に置いて、キッチンへ来てね。」
「あ、はい。」
「じゃ、葵、行こうか。」
まるで打ち合わせをしたかのような流れで、脇田君は私を部屋へ連れていった。
「荷物ここに置いておくから。それと必要なものがあったらいつでもこの部屋に入っていいから。」
「ありがとう。」
「あと、今日は来てくれてありがとう。すごく嬉しい。」
「え、どうして、」
「それは愚問だよ、俺は葵と長い時間一緒にいられることが嬉しいんだから。」
堂々とそんなことを面と向かって言われると、ハズカシイ。でも、…ウレシイ。人間の感情って不思議。
だけど、ウレシイとハズカシイでは、表面に出るのはハズカシイが上。だから、挙動がかなり…変になっちゃって。奇妙な視線の逸らし方をしてしまった。
「あ、エプロン、エプロン持ってきたんだ。お料理作るから、」
「ねえ、その前に、」
そう言って脇田君の手は私を抱えこむ。更には向きを変えて、唇が合わさった。
早業。
感心している場合じゃない。急いで下へ行かないと、何か良からぬことをしているって脇田母に思われちゃうよ。
もがいていたら、唇は離れ、代わりに言葉を発した。
「そんなに俺とキスするの、ヤダ?」
ちょっと悲しげなトーンだったから、思わず首を大きく左右に振って否定を表すと、脇田君は満面の笑みになった。
「じゃあもう一度。長い時間一緒に居れるかもしれないけど、二人っきりになるチャンスは少ないから。」
二回目は頭の中が真っ白になりそうなくらいのキスで、たぶん、横から見たら食べられちゃいそうなキスだったと思う。
来月は頭の中は何色になっちゃうんだろ?、って、ヤダ、私、何を考えてるんだか…。
私が脇田君とこうして過ごすようになって学んだことの一つが余韻。
それも、キスの余韻。
この先まで行くとどんな余韻があるんだろ…、って、やっぱり最近の私は変、イヤらしいかも。
キッチンへ行くと、脇田母が今日のメニューをざっと説明してくれた。
お菓子はケーキとアイスボックスクッキー。
それ以外はサンドイッチ、ローストポーク、サラダ、ミネストローネスープ、更にはラザニア。
聞いただけで眩暈がしそう。でも、脇田母に言わせると、ほとんどが下ごしらえだけしてしまえば後は楽らしい。面倒なのは実はサンドイッチかもなんて言っている。
少しすると楓さんが帰ってきた。
手には大荷物。どうやら今日の材料みたい。
脇田君は力仕事要員らしく、ボールの前に電動泡だて器と一緒に佇んでいる。
何でもケーキは卵白をいかにちゃんと混ぜるかが、スポンジの命らしい。
私はというと、ピーラーで野菜の皮むき。
脇田母の指示がいいのと、楓さんと脇田君のやり取りが面白いのとで、気付けば料理は8割がた完成といったところになっていた。
「あ、イチゴ忘れた。要、あんた買ってらっしゃい。」
「え、なんでだよ。」
「ここにいて一番役に立たないのはあんたでしょ。」
「役に立たないなんて、楓ちゃん、それはちょっと酷いわね。でも、要、暗くなってきたから楓ちゃんや葵ちゃんじゃあねぇ、悪いけど駅前までイチゴを買いに行ってくれる?」
強い口調の楓さんの後に、温和な口調の脇田母、…絶妙。
脇田君は楓さんが買い忘れたことに対してぶつぶつ言いながらも、買い物に出掛けた。
「葵ちゃん、要もいなくなったことだし、女三人で楽しくおしゃべりしましょうね。」
脇田君がいなくなると、脇田母はニコニコしながらそんなことを言った。
おしゃべりの内容は、最初のうちは私の家族の話とか、学校での話とか、当たり障りのないもの。
でも、突然どうしてそういう展開になったのか、困った内容になった。
「ところで葵ちゃんは要のどこが好き?」
「えっ?!」
「あ、それって私も聞いてみたい。ねえ、要のどこがいいの?」
脇田君のどこがいいか?そう言えば、私自身そのことを深く考えたことがないかも。
…どこがいいか?、どこが、
「あの、どこどこがいいから脇田君が好きってわけじゃあないんです。脇田君だから好きなんです。」
言ってて恥ずかしい、だから最後の方は声が震えたし、小声になったけど、これは本音。
だって、目が好きだから好きとかじゃない。脇田君っていう存在が好き。
知らないうちに私のテリトリーに入ってきて、気付いたら私の周りの一部になっていたから。
「うふふ、ありがとう、葵ちゃん。」
私の答えに何故か、脇田母は微笑みながらお礼を言った。
それから脇田君が間も無くして帰ってくると、そんな話題などなかったかのように二人はイチゴを見て喜んだ。