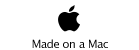はやる10月
はやる気持ち
僕の大切な従姉妹。彼女の名前は沢野井望。
子供の頃、彼女は将来僕のお嫁さんになると泣き叫んだことがあるそうだ。
当の本人はそれは幼い日の戯言、思い出したくもない事実だそうだが。
ともあれ昔は彼女がそういうくらい僕たちは仲が良かった。
あまり人には言えないが、そんな彼女を女にしたのは他でもないこの僕だ。
中学三年のときに家庭教師の大学生に恋をした彼女は、何を思ったのか大人っぽくなればそいつが振り向いてくれると思ったらしい。そして、どういう思考回路がそれを導いたのかは皆目検討がつかないが、大人の女になる=処女を捨てる、だった。
僕はその頃、その快楽を覚えたばかりで、たとえ望でも出来るのならば文句はなかった。僕と望は何度体を重ねただろうか?一桁でないことは間違えない。僕としても色々試せる相手だし、望とて性への興味があったのであながち僕との関係を拒否する必要がなかったようだ。
望みは困ったことがあると昔から僕を頼った。だから、セックスもその延長のようなもので、お互い知識の向上だったり快楽を求めれば十分だった。僕にとってその大学生とどうなったのかなんてどうでもいいことだった。
高校の合格発表のころ、望に修羅場が訪れた。相手は家庭教師。別れ話がもつれ厄介なことになったとき、結局僕が新たな男役で殴られることで解決した。なんでそこまで従姉妹のためにしなくてはいけないのか…正直言って腑に落ちない。
でもそれも含めて今現在、望には過去の貸しを清算してもらっている最中だ。子供の頃からの利子も含めて。
「もしもし、俺。」
『何?』
「あのさ、明日してもらいたいことがあるんだけど。」
『また、木内さん?もう、十分要には恩は返したじゃない。』
「まだだね。それとも望の彼氏に望の体の黒子の位置とか、どうすれば感じるかばらして欲しい?」
『悪魔!』
「何とでも。」
僕は望の痛いところを、いや気持ちいいところをよく知っている。そして、それを効果的に使うことができる。
「実は土曜日に一緒に帰ったんだけど、そのことを望の友達が見たことにして俺と木内さんの関係はどうなっているのか知りたがっているって聞いて欲しいんだ。」
『なんでそんなことをすんのよ。』
「男女が一緒に帰るってことは特別だって教えてあげて欲しいから。彼女でも分かるように、やさしい具体例を織り交ぜて。」
『嫌よ、そんな要の術中にはまる手助けをするのは。』
「そう、じゃあしょうがないね。望はいやらしいところに黒子があるから」
『分かったってば。最低!』
「なんとでも。ま、明日よろしく。」
望の男は僕の友人。そして、こともあろうか望はそいつが初めてという振りをしている。生理が終わる頃を見計らうということまでして。お陰で僕はちょっと望を揺さぶるだけで思い通り動かせる。変な嘘をついたばかりに…馬鹿な望。
月曜、望は言われたことをしっかりこなしたようだ。どうやら僕と話すのは嫌らしく、報告メールが届いている。
−−− 要へ。木内さんは要を"ただの友達"って言ってた。"ただの知り合い"じゃなくて良かったね。それと、男女が二人で一緒に帰るのは特別な関係の場合が多いって伝えておいた。本当はどうだか定かじゃないけどね。ま、木内さんがどう思うかは神のみぞ知るってとこだよ。−−−
文脈からなんとなく微かな皮肉が感じられる。まあいい、これからも活躍してもらわなくてはいけないかもしれないから、少しくらいは言わせておこう。
しかし"ただの友達"かぁ。さて、どうしたものか…。
僕は彼女と友達ごっこをするつもりはない。友達は入り口なだけであって、その先へ進まなくては。
たった一週間ちょっとだけど彼女に関して分かったことがある。
それは、思っていた通り穏やかなやさしい性格であること。そして何より僕に都合が良かったのは、疑う気持ちをあまり持ち合わせていないので、うまく流れをもっていくと思ったような反応だったり答えを返すことだ。
今日はどういう話をして、彼女を誘導すべきか…。
いつもの時間に合わせて話す内容を考えていると、彼女から初めて電話がかかってきた。
望がどういうふうに話したのか分からないけど、彼女の中の何かに変化が生じたのであろう。
僕の存在が彼女の中で大きくなっているとかだったら最高なのに。
けれども期待とは裏腹に、彼女と望の間で交わされた"友達にすぎない"という話の内容を丁寧に説明してくれた。
確かに手始めに友達になろうとは言った、でもそれは方便に過ぎない。
僕は初めて彼女に少しきつめな口調で質問した。それは、彼女にとって僕という友達の位置。
友達にも種類はある。大切な友達とか、メルトモとか…。
ずるい方法だとは思うけれど僕は彼女に二つの選択肢を与えた。
選択肢は『仲が良い友達』と『適当な友達』。彼女の普段の態度やら何やらを考えれば、前者を選ぶに決まっている。事実そうだった。でも今日はそれだけでは終わらせられない。
これからどうしたいのかを考えてもらわなくては。
そのために今後のことの質問を投げかけて電話を切った。
電話を切ったもののしっくりこない。今後もこのままでいいとか思われたら…、最悪だ。
やはり明日からはもう少し加速をつけなければ。
火曜、彼女がいつもと同じくらいの時間に教室に入ってきた。いつものように目を合わせ、次の瞬間にはさっと目を逸らし自分の席へ向かっていく。
一歩前進。
そのために、僕は彼女の元へ向かう。僕の姿を捉えた彼女の目が大きく見開かれる。
「おはよ、木内さん。」
「お、はよう、ございます。」
何だその歯切れの悪い他人行儀な挨拶は…。まあいいさ、君はいつも免疫のないことにはひどくびっくりするみたいだから。でも、今日はこれだけじゃない。僕は朝の挨拶をしにきたんじゃないからね。
「今日、一緒に帰ろう。どうせ同じ方向なんだから。」
彼女の返事は要らない。だから、言い切ってすぐに彼女の元を離れた。
自分の席につくと、彼女がこちらに向かってくるのが視界に入る。断るつもりだろうか?
けれども彼女の足は何故か望の席でとまった。何やら望に話しかけているようだ。
『あの木内さん』が、自ら進んで誰かと話している姿はそうお目にかかれるものではない。だから、周りの人間の目も知らず知らずのうちに彼女達に向けられる。
話している内容は?
やはり周りも気になるらしく、なんとなく静かになる。
それに気づいた望はわざとゆっくり大きな声で話し続けた。
「………その話の続きだと要はなんの友達になるの?」
「…………恋…かも…」
声が小さくて聞き取れない部分もあったけど、彼女は僕に対し友達以上の感情を持ってくれているようだ。
裏付けるように、望が僕をみて『聞こえた?要、これでチャラよ。』なんて言っている。全部は聞こえなかったけど、その台詞がでるってことは僕にとっていいことだろう。
彼女を見ると顔が紅潮している。そして、僕を見たとたん自分の席へ−逃げた−
それだけじゃない、普段はあんなにのんびりしているのに、脱兎の如く飛び出した。
鞄をしっかり携えていたということは、もう今日は戻ってこないだろう。
当たり前だけど今日は彼女と一緒に帰る。しょうがない、僕もサボるか。
下駄箱で捕まえた彼女の顔はまだ赤い。そして僕への感情を人前で言ってしまったことによる衝撃は大きいようで、未だ思考回路がショートしているようだ。
そんな彼女にこれからどうするのか聞いたところで当然答えはない。
−そうだカフェでも行って、温かいミルクティでも飲ませて落ち着かせよう。我ながら名案だ。−
そう思ってどこかへ行くことを提案すると、制服姿で街をうろうろすのはいけないことだとみなしている彼女に拒否された。
じゃあとっておきの選択肢をあげよう。
幸いにも、うちには母さんも姉さんもいなかった。母さんに限っては当分帰ってこないだろう。
ミルクティを出して彼女の気持ちが落ち着くのを待っていると、ようやく彼女が口を開いた。
「あの、脇田君、大切な話ってなに?」
僕が下駄箱で言った『大切な話』の真意を彼女が聞いてきた。
「朝の段階では、帰りに言うことは何度も考えて台詞が出来上がっていたんだ。でも、今はちょっと状況が違ってきていて…。」
「じゃあ、また今度にする?」
「いや、それも困る。今は追い風のような気がするから。」
「追い風?今は無風よ。」
分かってないな、君は。思わず彼女に向かって微笑んでしまう。
「望(のぞみ)に朝言ったことって、」
「のぞみ?」
「ああ、沢野井望さん。」
いつも望を沢野井さんて呼んでいるから、彼女の紐付けファイルが実行されるまでには時間がかかるようだ。そして、表情の変化がその実行完了を教えてくれる。
更に顔が赤くなり始めた。ということは朝のことを思い出しているんだろう。卑怯だけど、畳み込むチャンスかもしれない。
「あのさ、朝、望に言ってたことからすると、木内さんも俺のことを少しは好きになってくれてるって理解してもいいのかな?だとしたら話はすごく簡単なんだけど。でも、その前に一つだけ確認させて。昨日は俺の保身の為に望にただの友達って言ったらしいけど、何からの保身?」
「それは…、そのぉ…、脇田君の周りにいる子たちはどっちかって言うと華やかだったり、沢野井さんみたいにかわいいじゃない。私はいつだって、居ても居なくても大差ない人だから…、なんて言ったらいいんだろ?う〜ん、不釣合い。脇田君のイメージが落ちちゃうよ。」
何を言い出すのやら。君は自分を知らなさすぎるよ。僕のほうが君には不釣合いだ。
「木内さん、そんな馬鹿なことを考えてるんだ。」
「馬鹿なことなんかじゃちっともないよ、私には。」
少し強い口調に、彼女にとってそれがいかに大きな問題かを理解する。
「ゴメン。でも、俺には木内さんがいるかいないかは雲泥の差なんだけど。この間言った好きだっていう気持ちは本当だし、気持ちを伝えるだけで、満足なんてしていない。出来ればいつも傍にいて欲しいんだ。」
「私なんかすごくつまらない人間よ。きっといつか、ううん、すぐにイヤになるわ、脇田君。だったら…、」
イヤになるわけがない、君そのものが好きなんだから。気づけば目で追って、知らないうちに好きになった。それがようやく手の中に納まろうとしているのに。
君は知らないんだね、この一週間で更に僕が君を本当に体の一部のように取り込んでしまいたいと思っているとは。必要不可欠なんだ。
「泣かないで、木内さん。木内さんを泣かせたくて話をしているわけじゃないから。ただ、付き合ってみよう。」
勿論泣かせるつもりなんてかなったのに彼女の目からは涙が落ちる。
僕の気持ちが伝わることを祈りながら、彼女の気持ちが安らぐのを待つ。
少しして、彼女がぽつりと呟いた。
「すき」
「えっ、」
主語も目的語もない彼女の精一杯の言葉。ただ、自分の耳に都合よく聞こえているだけではないかと思わず聞き返してしまう。
「すき」
今度は目を見て伝えてくれた。
彼女は僕を好きだと言っている。じゃあさっきの答えの返事は?
「それって、付き合うことはOKって返事?」
「分からない。でも、すき。」
「難しいなぁ。」
「ゴメンナサイ。」
じゃあ僕の好きを君にあげるよ。
「いいよ、それだけ分かれば。ちょっと立って。」
「立つの?」
「そう。ソファって隣に座るにはいいけど、向き合うにはいまいちだから。」
彼女は素直に立ち上がった。そして僕の方に向く。涙が止まっても目が赤い。そんな顔すら愛しいと思ってしまう。
それを体現するために彼女をやさしく抱きしめた。
「すき」
小さく彼女が呟く。
「分かってる。だから木内葵は俺のもの。」
彼女はおとなしくしている。これは肯定と見なしていいのだろう。
更に僕は畳み込む。
「木内さん、これからは葵って呼んでもいい?」
「はずかしい。」
「それって、恥ずかしいけどOKってことだよね。」
「うん。」
彼女が答えと同時に頷いたのが触れている部分を通して伝わってくる。こんなにも気持ちが満たされたのは久しぶりかもしれない。
たまには望に奢ってあげるのもいいだろう。