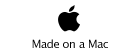はやる10月
決行は日曜日
僕が彼女を好きな理由…そんなのは本能に聞いてくれ。
そうとしか言い様がない。
一つ言えるのは、今までと明らかに経緯が異なる。
今までは、相手が自分に好意を寄せている−これから全てが始まっていた。
つまり相手から自分に対するアプローチがあった。好かれているのだから、それから先は簡単。10代中ごろの欲求を満たすのも簡単だった。
そう思っていた。
中には違う習慣を持つ民族・部族もいるが、多くの民族・部族の中で男は狩猟を行なってきた。冷凍トラックで肉が運ばれてくる現代でも、DNAの中にそれが残っていることを彼女は僕に教えてくれた。
彼女は木内葵。クラスの中でも目立つ集団には決して属さず、自分のペースで毎日を送るタイプ。窓際の席にいるせいか、日なたでまどろんだり、転寝したり。
その姿はとても平和的で、見ている僕まで幸せを感じてしまうから不思議だ。
最初は気づけば目が追っていて、そのうち密かにその姿を視界に捉えるのが楽しみに変わっていた。
見るだけで幸せだった日々、それが彼女の艶やかな黒い髪に触れてみたいという欲求へ変わるまでの時間はそう長くはなかった。しかし、僕の欲求はそれに留まることを知らず、赤みを帯びたふっくらとした唇に自分の思いを重ねてみたいと思うようになっていた。
僕にとって彼女は獲物。昔の人間がどう狩をしていたのかは知らない。でも必ず獲るために僕は彼女の行動パターン、聞こえてくる会話を追った。ある意味危ない人間そのもの。
その結果、僕が知り得た情報は−
彼女の好きなこと、それは映画。しかもメジャーなタイトルではないようだ。
彼女の好きな飲み物、それはオレンジジュースとミルクティ。よく紙パックの500mサイズにストローを通して飲んでいる。
彼女に興味を持っている人間は僕だけではないだろう、残念ながら。
だからこそ、2学期になり何故か彼女がよりきれいになりだしてあせった。もしかして"誰かに恋している"のではと思ったから。
僕には同じクラスに従姉妹がいる。彼女は沢野井望。結構可愛かったりする。が、性格は顔とは相反している。けれども世の中顔が与える印象は恐ろしい。望は傍目には顔も性格も『かわいい』ということになっている。
そんな望に僕はいくつかの貸しがある。正直言って、今まではそれを精算しようと思ったことはなかった。しかし望は、数少ない木内さんと話をする人間なので、僕の持ち駒になってもらうことにした。
「望、木内さんともう少し話せよ。」
「分かってるってば。でも、今まで大した内容の話をしてないんだから急には無理だって。」
「じゃあおまえの母さんに、今まで俺がついた嘘を全部暴露するだけだな。」
「止めてよ。あんたって本当に性格悪いわね。」
「お前ほどじゃないよ。」
接点が欲しい僕は時折望という鵜のコントロールを厳しくした。
それから間もなくして、鵜は鮎を飲み込んできた。
木内さんは次の日曜日に単館の映画館へ行くらしい。僕としては辛いが、彼女は朝一の上映に行くとのこと。辛いけれど、朝一ならばその後にランチを誘えるだろう。
当日は緊張につぐ緊張。大前提として、彼女と僕は約束をしているわけではない。彼女が当日予定を変更することだって起こりうる。だから、空振りになる可能性もあるし、彼女に声をかけそびれることだってある。最悪なのは、声をかけるところまで進んだとして、その後僕自体を認識されなかったら…。立ち直れないな。
そんな最悪なことばかりを思っていると、僕の視界が彼女を捕らえた。心拍数が上がる。全ての言葉を忘れそうだ。
やっとの思いで出した言葉。そして彼女の僕に対する認識度が明らかになる。予期せぬ場所で声をかけられても顔と名前の紐付けがすぐにはなされないといったところだろう。
悲しい現実。
けれども、そんなことで感傷に浸っている暇はない。
僕−脇田要を印象づけなくては。
単館映画館とうのは不便で、チケット購入時に番号札を渡されその番号にそって入場をする。せっかく彼女と同じ映画館に来たのに彼女と一緒に入れない。
そこで彼女の番号を見せてもらう。
28番。僕は51番。
「木内さん、いい位置に座ってよ。もし隣が空いていたら座らせてもらうから。」
苦肉の策。ま、僕の考えるところの映画館は、よっぽど満員でなければ隣同士詰め合わせることはないという前提。だから、かなり高い確率で僕は木内さんの隣に座ることになる。
「41番から60番の方入場下さい。」
木内さんが入ってから、僕の入場が許されるまでの時間は実際には数分。けれども僕には何十分にも思えた。中に入るなり、薄暗い館内で彼女の黒髪を捜す。そして、即座に隣の二席も空いていることを確認する。
なんだかんだ言って、ここまではうまくいった。問題は折角隣なのに、何も話しかけることができない僕。
そんな空気を嫌うように彼女が席をたった。正直言って有難い。やはり木内さんが隣にいると考えがまとまらないから。
彼女と入れ替わるようにトイレへ向かい、更に考えをまとめる。僕としては、こんなチャンスが何度あるか、というよりもうないかもしれないので、どんなことがあっても自分の気持ちを伝えることを決心する。
彼女は慎ましやかなのかすっ呆けているのか…、今まで言葉を交わしたことがなかった僕には分からない。彼女に飲み物を渡してもそっくり返されてしまうし、なんだか今までの女の子達とかってが違う。
そんな彼女が代金を支払おうとした瞬間、僕に絶好の好機が訪れる。
利き手ではない左手すら動員して、僕は彼女の右手がかばんの中の財布に手を伸ばす前に捕まえた。
彼女には代金は不要であることを伝え、僕自身はしっかり代価を頂く。
"木内さん、ジュース代なんていらないよ。これで十分。"
掴んだ手を映画が始まる頃には、上から包み込むことに成功した。
彼女がその行いを拒絶しないのは何故だろう?−
映画に見入っている、それとも手を握られ慣れている…分からない。
彼女は映画が終わるとすぐに立ち上がる人ではないようだ。エンドロールが流れ館内に鈍い灯がともる。
教室では見たことがなかったが、感情的なようで涙をハラハラと流している。右手を放すと、自分の鞄に手を伸ばしごそごそとしている。ああ、ハンカチかぁ。
変質者っぽいけど彼女の涙が欲しい。僕はハンカチを差し出した。
彼女は洗って返すと言っているけど、本音としてはそのままの状態で返してもらいたい。
ロビーにでることを促すと、驚きの目で見返された。やはり彼女は僕とここで別れる気らしい。残念ながらそうする気はさらさらないよ。ロビーでも体裁よく別れを切り出そうとしている。そこは敢て言葉を遮り対処。僕も必死なわけで。
だからかもしれない、昼食に誘ったのに彼女から否定の言葉がでると思った瞬間さらっと自分の気持ちを口にしていた。
僕は生まれて初めて人に好きだという気持ちを伝えた。しかも映画館のロビーなんて場所で。
その後僕はご尤もな講釈をたれ、彼女と近くのカフェに入った。
オーダーをしてから彼女は勿論のこと、僕も何をはなしていいか分からない。重い空気。
これじゃあ傍から見たら別れ話をした後のカップルにでもみえるんじゃないだろうか。
ひとまず料理が運ばれたことで、僕らには食べるという目的ができる。その後は…
彼女が食べるのを見計らってまずクリアにすべきことを聞く。それは彼女がここ最近きれいになった理由。見ている限り男はいないと思う。だとしたら恋でもしているのか?
僕の質問に彼女は素直に好きなヤツはいないと言う。気になるヤツに関しては首をかしげながら思いをめぐらせている。その様子は襲いたくなるくらい可愛い。気になるヤツがいようと構わない、この表情も含めて全てを僕のものにしよう。そう思うと、やはり答えを求めてしまう。
自分の気持ちを言ってしまうと気は楽で、寧ろ相手の出方を知りたくなってしまう。
彼女は尤もな理由である『僕をよく知らない』という言葉で僕との距離をおこうとした。−−−それでは今日という日の意味がなくなる。
最終的には友達という言葉で彼女を丸め込み、僕は自分自身を満足させた。
ただし、次のステップは親友じゃないけどね。