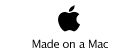色づく11月、月曜日
聖夜
色づく11月、月曜日
家族がいるところに彼女が遊びに来るというのはこういうものなんだろうか?
いまいちよく分からない。
姉貴も彼氏を家に招いたことなんかなかったし。
日曜の昼下がり、うちのリビングには父さん、母さん、姉貴と僕、そして葵がいる。
テーブルには葵が持参した焼き菓子と、母さんが用意した飲み物がならび今まさに午後のお茶を楽しもうとしている。
こういう状況ではどういう話をしたらいいのか…。
話題を考えていると、姉貴が口を開いた。
「文化祭の準備はすすんでる?」
「あ、はい。私の仕事はもう全部終わりました。」
「良かったね。ってとこは、事前準備組だったのね。」
…、『〜のね』、って、姉貴でもそういう話し方をするのかよ。
どうやら僕は怪訝そうな顔で姉貴を見ていたようで、それに気付いた姉貴に鋭い視線で睨まれた。
けれど葵を見る目は全く違う。
「文化際が終わったら来月はいよいよクリスマスね。うちは毎年家族で過ごしてるんだけど、葵ちゃんは?」
「特別なことはうちはしないです。兄とかはクリスマスが近づくと何だかそわそわしてますけど。」
「そうなの?じゃあ、24日うちに遊びに来ない?毎年ケーキを焼いたり、料理を作ったりしているんだけど。色々作るの、楽しいよ。ねえ、お母さん。」
「そうね、みんなで作ったほうが楽しいものね。」
「でも、せっかく家族で、」
葵のお断りモードの発言を敢て遮るように、姉貴は言葉を発した。
「そうだ、どうせ次の日休みなんだからうちに泊まっていけば?要の友達だとNGかもしれないけど、私の友達なら大丈夫でしょ、おうちの人も。」
「そうねぇ、もし良ければおばさんがおうちの人に電話をするわよ。」
葵のタジタジモードをお構いなしに、二人が言葉の応酬を続ける。
ある意味すごい。やはり親子。息がピッタリ。
そんなことをボーっと考えていると、最後はあんたが一押ししなさいと言わんばかりの形相で姉貴が僕にふってきた。
「ね、要、一人でも多いほうがいいわよね?」
「え、あ、うん。葵さえ良かったら。うちは全然構わないから。」
「あ、じゃあ、家で母に話してみます。」
母さんと姉貴はその返事に満足したのか、二人で既に何を作ろうか話している。葵は家族に話すといっただけで、まだ来るとは決まってないのに。
でも、あの人達のことだ、きっとそう仕向けてしまうんだろう。
クリスマス、一ヶ月も先の予定…。
そして、『彼女』という言葉への肯定。
成行だからこうなることを受入ていたような葵から、少しづつ当事者としての葵に変わったような気がする。
相変わらず、雨脚は強い。天気予報によると台風並みの低気圧だそうだ。
ようやく家族から解放されて僕の部屋で音楽をかけてはみたものの、ボリュームをいつもよりは上げないといけない。
葵と話す声も聞き取りづらいくらいの雨の音。
全てが僕にとって好都合。
何度も葵の言葉を聞き返すのは悪いからと隣に近づく。ベットを背もたれに、彼女との距離は彼女の緊張が伝わるほど近づいた。
葵もこの距離で男女が並んでいたら、コトに及ぶ可能性があることを理解しているんだろう。
「この間のドラマの続きみる?」
「あ、うん。なんかアメリカのドラマって発想が面白いよね。」
前回、僕はアメリカでドラマシリーズとして放送されている番組を葵と見た。たまたまうちのケーブルテレビのとあるチャンネルでやっているやつで結構面白い。
昏睡状態から目覚めた主人公に、不思議な力が備わり、それに伴い様々な出来事に巻き込まれるというものだ。
映画は長い。しかも、レンタルで借りてくると映画館での尺より長いものとかもある。ドラマは正味45分弱。そして、アメリカのシリーズものは面白ければいくつものシーズンへと発展していく。
変な表現だけど、この結構面白いドラマは葵へのとてもいいえさになる。
再生の準備をしながらさっきのフォローと確認を。
「クリスマス、何か他の予定があったら無理しないで。うちの姉貴は結構自分の思い込みでものを言うからさ。母さんにまでああ言われると断り辛いかもしれないけど、イヤだったら断って。」
「あ、うん。でも、ケーキとか作ってみるの楽しそうだから…。うちでお母さんに聞いてみる。」
「分かった。」
どうやら葵はさっきの話を受け入れる方向で考えているようだった。やはり、特別な日に家族がいるとは言え、葵に会えるのは嬉い。しかも、泊まっていくなんて…。
何を思って、11月だというのにこの話をしたのか分からないが、僕は姉貴に純粋に感謝した。