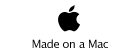作法教室
ひみつ
「へえ、東郷のお嬢さんは家柄なんてどうでもいいんだ。それに公方のお嬢さんはデザインの勉強かぁ。二人にはここに来てもらって悪かったな。」
わたしが口を滑らせてしまった数分後、邦和が歩きながら呟いた。
「ねえ、怒らないの?」
「なんで。」
「だって、お兄さんのお嫁さん候補なのに。」
「その前に一人の人間だよ。」
「ね、じゃあさ、今の話聞かなかったことにしてくれる。」
「ああ、俺と芙美花の間だけの秘密な。」
二人の秘密。なんだかその響きに胸が高鳴った。
「そろそろ帰るか。」
邦和が自然に差し出した手に、今度は何の抵抗もなく手を伸ばした。この手を握るのも悪くないなんて思いながら。なんでだろ?だけどもっと不思議なのは駐車場までの距離。確かに歩いた。なのに、すぐに着いてしまったような気がしてならない。
車に乗り込むと、邦和は一旦入れたエンジンを何故か止めてしまった。どうしたんだろ?、不思議に思って横を見ると邦和の表情はまるで苦虫を噛み潰したようだった。
「本来の血統なんてこと言ってるから…」
そして小さいながらもそんな言葉をもらした。
「本来の血統?」
「ああ、本来の血統。せっかく話してくれた御礼に、どうして今回芙美花がここに呼ばれたかも含めて、俺の知っていることを教えてやるよ。当事者が知らないなんて不幸だからな。」
—まず、おまえのばあさん、旧姓、二条芙美に関してからだな。全ての始まりは彼女だから—
全ての始まり?
邦和は一息吸い込んでから、さっきまでの表情とは全く違う優しい顔でわたしを見た。そして、確かに全ての始まりがおばあちゃんだと口にした。
— 昔、二条家という華族には四人の息子と一人の娘が生まれた。その一人の娘というのが芙美さんだ。彼女は他の四人と年齢が離れていたし、一人娘ということで大層父親に可愛がられた。まさに目の中に入れても痛くない存在だっただろう。そして二条氏は、自分がこの世を去った後の彼女の幸せすら心配だった。華族という身分が故に妾を持つやからも多い中、本当の家庭を持てる家へ嫁がせたかったそうだ。だからと言って良識や道徳を重んじるだけで財力がないのでは先が見える。二条氏にとって一人娘の嫁ぎ先は大きな問題だった。芙美さんが二歳になった頃、ようやく二条氏は家柄・財力・道徳感において彼の希望以上の嫁ぎ先を見つけた。当時力を持ち始めていた軍人には嫁がせたくないという思惑も手伝い、芙美さんが三歳になる頃には華族会館で両家の間で正式に結婚が決まったことを宣言したそうだ。先方も二条家との結びつきには諸手を挙げて賛成だったらしい。
当の芙美さんはというと、華族の娘らしく、いやそれ以上に教育がなされた。作法だけでなく当時としては珍しい外国語。しかもその外国語は日本に駐在する外国人に習っていた。彼女はそこで言葉だけではなく、西洋の思想も感じ取ったんだろう。
二条家と芙美さんが嫁ぐはずだった家は、戦後の財閥解体でも衰えることのない力ある家だった。残念ながら芙美さんの二人の兄は戦争でなくなってしまったが。戦争も最後の方になると当時は特権階級の華族でも兵役を逃れることは出来なくなったからな。
16歳になった時、芙美さんは二条氏から結婚について知らされた。華族制度が廃止されたにもかかわらず。否、むしろ廃止に伴い、これ以上力を失わないよう家同士が結びつくのは当然だったのかもしれない。大学進学を希望していた芙美さんに、女学校卒業後にあった道は結婚だった。実際にはそうはならなかったけど。 —
「え、そうならなかったって、じゃあ、」
「そうなってたら、今の芙美花は生まれてなかっただろ。」
「あ、そうか。」
「それにここまで話したら普通気付くだろ。芙美さんの嫁ぎ先は西園寺家。俺のじいさん。兄貴の一回目の嫁選びは親父が主催したからああいう結果に終わったけど、今回は違う。出来レースなんだ。最初から相手は芙美花なんだよ。芙美さんと仲が良かったばあさんが仕組んだ、」
「西園寺家のおばあさんが、」
「そ、芙美さんは女学校卒業後消えた。しかも、うちのばあさんとじいさんが惹かれ合っているのを知っていて。更には二人が結ばれるよう取り計らうことも忘れず。かなり計画的に家出したんだろうな。とても筋金入りのお嬢さん育ちとは思えない人だ。」
あのおばあちゃんが…、なんて思っている場合じゃなかった。
「ね、いくらうちのおばあちゃんとあんたのおばあさんが仲が良かったとは言え、どこをどうしたらわたしがあんたのお兄さんと結婚することになるの?」
「だから本来の血統のためだよ。」
「今更本来の血統だなんて。」
「だけど今なんだ。芙美さんには娘は生まれなかった。しかも孫で女は芙美花だけ。西園寺家の息子は適齢期。お互いの事情を知るばあさん同士はまだ健在。ある意味条件が揃ってるだろ。しかも、うちのばあさんが芙美花の写真を見たときに、あまりにも芙美さんの若い頃に似ていてびっくりしたんだとよ。名前だけでなく、顔まで似てるって。」
「でも、だからって、わたしにだって好きな人がいる可能性だってあるじゃない。」
「だから、まだ高校に通っている今こんなことをしてるんだろ。広い社会に出る前に話を固めちまうつもりで。そうすれば処女性も保てるし。」
「…そんな、」
そんな話があがっていたなんて…。うちじゃあ誰もそんなことを言ってなかった。
「暗い顔すんなよ。俺が言うのもなんだけど兄貴はいい男だから。まあ、顔は俺のほうが良いけど。普通は玉の輿にのれるんだから喜ぶとこだろ。」
「違う。わたしは自分でその人を知って、男の人として好きななるか決めて、恋をしたい。恋をしたところで、相手にされるかどうかは分からないけど、そういうのを含めて楽しみたいんじゃない。振り向いてもらいたいから色々努力したりするんだろうし。必要以上に緊張したり。」
ここまで話したら、急に目から涙がたれた。
「泣くなよ、芙美花。兄貴との事は100%決まっているわけじゃあないんだし。それに芙美さんは何もお前に言ってなかったんだろ?それは芙美さんの昔からしたら、芙美花にそんなことを強制したくないっていう考えからじゃないか。」
「わたしがそう思ったところで、あんたのお兄さんは?いい人なんでしょ?だったらおばあさんの為、おうちの為に何の感情も持たないままわたしと結婚を進めるかもしれないじゃない。お金があっても気持ちが全くない結婚なんて…」
「まあ落ち着けよ。今、俺が言ったことは全部忘れて兄貴が来るまで、今までと同じように過ごせ。大丈夫だから。」
何がどう大丈夫なのかは全く見当がつかなかったけど、何故か邦和を信じられた。最後に大丈夫だからと言ったときの顔があまりにも優しかったから。