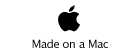作法教室
告白
邦和の話を聞いてから、わたしが普通に過ごせていたかどうかは分からない。だけどしょうがないと思う、だって内容が内容だから。でも、邦和は言った、何とかしてくれるって。楽観的なわたしはだから大丈夫って言ってる。一方悲観的なわたしは…、邦和一人じゃあどうにもならないって言っている。ううん、分かってる、こういうことは小さな力じゃあ大きな力に敵わないって。
邦和は一体全体どうやって…
わたしの晴れ晴れしない心とは反対に一樹が到着する日の空は快晴だった。ここまで快晴だと、空に恨みはないけれど何かの嫌味に思えてくる。ついでに空同様犬養さんたちに罪はないけれど、ここに来て初めて朝ごはんを残してしまった。
「本日は一樹様がお見えになるまで予定はございませんので、ゆっくりとお過ごし下さい。」
石川さんからは、朝食後今日は何の予定もないと告げられた。残念ながら夕食後には歓談会があるようだけど。ま、せいぜいその時までは自分磨きをしておきなさいということなんだよね、一樹のために。
— コンコン —
なんとなく扉は叩かれると思っていた。そして叩いたのが誰だかも分かる。扉を開けるとそこには予想通りの人物がいて、なんだか目にじわっと水分が滲んでしまった。
「何景気悪い顔してんだよ。」
「ばか。」
「いきなりばかはないだろ、って、え?」
邦和が驚いた。そりゃあそうだよね、だけど、わたしの方がもっと驚いたかも。まさか邦和に抱きついてしまうなんて。
「誰か来ると拙いから、中に、な、」
突然のわたしの奇行に邦和は動揺することなく優しく言葉をかけ、中へ入るよう促した。なんか優しいときのお兄ちゃんみたい。すっごく落ち着く。
だからかな、促されて座った場所がベッドの縁でものんびり構えていられるのは。だだ横に、隣り合って座っているだけ。なのに今、言ってしまいたいことを全部分かってくれているような感じ。
「落ち着いた?」
「うん、たぶん。」
は?へ?
「このほうがもっと落ち着けるから。力を抜いて。」
えっと、そうなの?これって…
これって押し倒されているってやつ?だったりして?
でもちょっと違うか。確かに最初はわたしの想像していた押し倒すってやつだったけど、邦和はその後隣にふわっと寝転んだだけだから。
目が近い。今までのどんな時よりも。違う意味で落ち着かないよ。
「兄貴と話した。」
何を?なんて聞く必要はない。分かりきっていることだから。ただ聞きたいのは結果だけ。
「分かったって言っていた。」
「何を?」
「芙美花の気持ち。兄貴は、もし芙美花が自分と同じようにばあさんの気持ちを優先させたいと思っていたのであれば、この出来レースに乗るしかないって思っていたんだとさ。」
「ってことは、」
「そ、このレースからは降りるってこと。」
「当人同士にその意思がないとしても、」
「大丈夫、俺を信じろって言っただろ。」
えっ!?、えー
横たわった体を邦和に引き寄せられてる?って俗に言う抱きしめられてる?
心臓ひっくり返りそう。
「あのさ、」
ようやく絞り出した声は震えているのが自分でも分かる。
「黙って。少しの間。」
邦和はそう言うと、ベッドとわき腹の間にもぐり込んでいる腕で更に引き寄せ、空いている手で頭をなでてくれた。
心臓はまたドキドキしているけど、なんかいい。この間から邦和の手はなんだか優しい。
でも、わたしの心臓はまた鼓動を早めた。だって邦和、もしかしなくてもわたしの頭にキスしてる?
「あの…。」
どうしよう、何て言えばいいか分からないな。
「自分の周りにいないタイプだから物珍しいだけだろうって、」
わたしの言葉を押し退けて、邦和が頭上でぶつぶつと何か言い始めた。まあ、わたしの言葉は続かなかったから、押し退けるも何もないけれど。
変な呪文みたい、何のことやら。
「しかも現役女子高校生だなんて、」
頭おかしくなった、邦和?そんなことを思っていたらバレちゃったのか、より強く腕をまわされた。
「好きだ、」
えっ、やっぱ頭打ったとか。
「ん、んんー」
初めてにはそれなりに夢があった。
夜空に星が輝いていて、夜景はきれいで、それからヨーロッパの庭園にあるみたいな可愛いベンチに二人寄り添って、最初は額に優しくチュって。で、次に同じように唇にもチュって。それで抱きしめてもらったら、今度は言葉。とっても甘い言葉を囁かれて、その後、ちょっと大人なキス。
確かに、ここの夜空は毎日星が輝いているよ、ついでに邦和には抱きしめられている。だけど、やだ、涙が出てきた。
「泣くなよ。」
「だって、邦和がこんなことするから。酷いよ。」
「酷いことをした覚えはない。ただ、素直に好きだっていう気持ちを表しただけなんだ。」
「だってわたしは邦和のこと、」
「俺は好きだ、芙美花のこと。芙美花の望んでいる運命の悪戯とかそんなのは無理だけど、本気で好きだから、本気で付き合いたい。」
「…そんな、いきなりキスされてあたふたなのに、畳み込むようなこと言わないで。それに、わたしまだ高校生だから、付き合うとかそういうこと。」
「本気で言ってるのか?今時。周りを見てみろよ、普通に高校生のカップルはいるだろ。」
「でも、わたしと邦和じゃあ家に差がありすぎるし、邦和、大学生だし。」
「別にそんなの関係ないだろ。家のことは俺は次男だからあんまり関係ねえし、年齢からして大学生なのは当然なんだから。」
「だけど、」
「だけど?」
「だからぁ、わたし、キスだって初めてだったんだから、その先なんて不可能。付き合うって最終形はそれでしょ?大学生と高校生じゃあ、大学生の速度に合わせることになるんでしょ?」
「ばーか、最終形はそこじゃない。それに芙美花がイヤなら、芙美花の為なら俺は無理強いなんかしない。ただ一緒にいて抱きしめられれば十分。」
「抱きしめる?」
「そう、いつも俺が傍にいるって伝える為に、抱きしめたい。」
「でも、やっぱり付き合うだなんて、良く分からないし。」
「じゃあ、そう考えなければいい。一緒にいれるときに同じ時間をこうして過ごすと思えばいいから。」
「わたし、抱きしめてもらっているだけじゃなくて、星がきれいなところとか、夜景が見えるところなんかにも行きたい。」
「芙美花が喜ぶなら、連れてってやるさ。あんな可愛い顔でケーキをぱくつくなら、ケーキ屋だっていくらでも。」
「邦和、本当にわたしのこと好きなの?」
「だからさっきから言ってるだろ。」
「わたしは最初のときより嫌いじゃないけど、好きかって聞かれても良く分からないとかだよ。」
「大丈夫、芙美花は俺を絶対に好きになる。好きにさせてみせるよ。」
すごい自信じゃない。わたしも本当は嫌いか好きかを聞かれたら、好きだけど、それが男の人に対する恋かって聞かれると、正直まだ分からない。そんなわたしをつかまえて、そこまで言い切るなんて傲慢?でも、それが邦和なんだね。