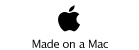作法教室
公方清佳(くぼうさやか)様の場合
敦美さんとは例の一件依頼、とても仲良しになった。(もしかしたら相手はそんなこと砂粒程も思ってないかもしれないけど。)正直言って作法を学ぶことよりも、敦美さんと仲良くなれたことのほうがうれしい。
お父さん、お母さん、おばあちゃん、ついでに兄達、ごめんなさい。
だけどここに来てから2週間目、否応なしに作法は覚えている。
例えば、お茶の席で畳の目を16個数えたところに座ることとかなんだとか。
でも、わたしは顎を使って16目を数えるけど、他の四人はすんなりと正確な位置に座るから不思議。やっぱりこの人達が今更作法を学ぶ必要性はないよ。
そうそう、珠樹のあの不適な笑みも消えないんだよね。わたしは別にあんたとは競ってないってばって言ってやりたいとこだけど。
特にお茶とか書道とかの正座ものの後、わたしが立ち上がろうとすると珠樹は微笑む。痺れがマックスなんだからふらつくのはしょうがないじゃない、と声を大にして言いたいけど、お嬢さん達は誰一人として痺れてないみたいで、当たり前のように涼しい顔をしている。
敦美さんにどうしてか聞いてみたけど、一言、『慣れかしら?』とのこと。全然参考にならない。
おばあちゃんが着物を用意してくれた理由が分かったのは、2週目の着付けの時間から。
お金持ちなんだから、専属の着付けの人を雇えばいいと思うのはわたしだけ?なんでか、自分で着れるようにならなきゃいけないらしい。
しかも、おばあちゃんが着物をいくつか入れてくれた理由も分かった。着物にもフォーマル用とか普段用があるんだって。
「芙美花さん、随分古そうなお着物をお持ちなのね。」
わたしに何故か敵意むき出しでこんなことを言ってくるのは、そう、珠樹。
「だって、おばあちゃんのだから。」
「まあ、随分保存が行き届いているんですね。それに、こんな織物は逆に今ではなかなか手に入らないから、羨ましいわ。」
お嬢様に羨ましがられるとなんだか嬉しい。ついでにこの褒めてくれた人は公方清佳さん。
「全部おばあちゃんが用意してくれたから、逆に新しいものは全くないんですけどね。」
「芙美花さん、見せてもらいに行ってもいいかしら?」
「あ、いいですよ。」
「まあ嬉しい、ありがとう。」
「じゃあ、今日の3時過ぎくらいに。」
「ええ、お邪魔させていただくわ。」
今まではご挨拶とちょっとした社交辞令しかかわしたことがなかった清佳さんだけど、部屋に来てもらって会話が続くかな…。ちょっと心配。
それでも、お招きしたからにはちゃんとしないと。
飯塚さんにお願いして、紅茶とクッキーを3時ちょっと前に届けてもらえるようお願いした。
お願いしたものは3時5分前にやってきた。今日のクッキーはココアとバニラ。飯塚さんはまだ余熱が完全にとれていないと申し訳なさそう。でもそれって、さっき焼きあがったってことだから、わたしとしてはすごく嬉しい。
テーブルに並べて待つこと数分、清佳さんがやってきた。
ちなみに清佳さんは21歳の大学3年生。
珠樹、敦美さんとは違って、髪の色がダークブラウンで縦巻のパーマがかかってる。自分の顔のつくりをよく知っているのか、すごく髪型が似合ってて素敵。
「今日の着物、とっても素敵だったわ。それに帯も。あのコーディネートは芙美花さんがご自身で?」
「コーディネート?そんなご大層なもんじゃないですよ。着物と帯はおばあちゃんのメモ通りに。あと、紐とかは適当に選んだだけですから。」
「帯揚げと帯紐はご自分ででしょ?、すごくセンスが良かった、芙美花さん。」
「ありがとうございます。」
「是非、他にお持ちのものも見せてね。」
「あ、どうぞ、どうぞ、適当に広げて見てください。」
清佳さんは、ちんぷんかんぷんのわたしに、それぞれの着物の名前と特徴を教えてくれた。ちなみにわたしが持ってきたのは、今日の以外に黄八丈、紅型、そして縮緬の訪問着らしい。
どれも素晴らしいものだと褒めてくれた。
「清佳さんだったら、わたしの着物、どうコーディネートします?」
この質問に、清佳さんの顔がぱあーっと明るくなった。
「いいの、そんな出すぎたことをして?」
「いいも悪いも、寧ろ教えてもらいたいぐらいですよ。だって、清佳さんの普段の服装ってすごくセンスがいいもん。」
「えっ!」
「わたし、何か変なこと言いました?」
「だって、センスがいいって…」
「あ、本当ですよ、いつも思ってましたから。」
お世辞抜きで清佳さんは、本当にセンスがいい。
服に着られているのではなく、服をしっかり着こなしている。
「ありがとう、芙美花さん。そうおっしゃってもらえると嬉しいわ。だって、わたくし…、」
「だって?」
しばし沈黙。
ここまでの会話って何か変だった?清佳さんは、何を躊躇っているの?
「きっと話してしまえば楽になるのよね…。」
その言葉はわたしへ向けられたというより、自分自身に向けた言葉のようで…。
そう言った後の清佳さんは、一皮剥けたような、というか、なんて言っていいのかは分からないけど、今まで目にした清佳さんとはちょっと違う感じだった。
「芙美花さんは覚えてくださっているかしら、わたくしの学部?」
「確かフランス文学部…、でしたっけ?」
「はい、そうです。でも、フランス文学を学びたいからこの学部を選んだわけではないんです。」
「というと?」
まだ大学へ行ってないから、(あ、本人的には進学希望なんだけどね、)清佳さんの言ってる意味がよく理解できない。学部名って勉強する内容が表記されてるんじゃないの?ほら、法学部だったら法律の勉強、みたいな。
「フランス語を勉強したかったのと、家のものに怪しまれずにフランス語の本を買うためです。」
「あ、じゃあ、フランス文学部でいいんじゃないですか?」
「そうね、でも、本って言っても、デザイン画とか、フランスのデザイナーの本とか、そうね、Gabrielle Bonheur Chanel、あ、ココ・シャネルって言ったほうが通じるのかしら?とか、色彩の本とかなの。」
「ふーん。」
清佳さんの話からすると、清佳さんはすごくデザインに興味があるみたい。ま、お嬢様道楽ね。
「ふふ、でも、自分が欲しいからじゃないの。わたくし、大学を卒業したら、今までこっそり貯めたお金でパリへ行こうと思っていて。純粋にデザインの勉強をしたいの。」
「へ?、でも、西園寺家のお嫁さんテストに来てるじゃないですか?」
「ええ、お父様からの命令だから。でも、芙美花さん、最初の日におっしゃったじゃない、作法教室へ来たって。実はわたくしもそう思うようにしているの。第一、わたくしが選ばれる確立はかなり低いわ。」
「いいえ、そんなことはありません。清佳さんは皆さんの中で一番髪の色が明るかったり、色彩が豊かだから、もしかしちゃうと、西園寺家のご子息の目に一番最初に入っちゃうかも。」
「そういうものなの?」
「…なんとも分かりませんが。」
「ま、その時はその時だわ。今はそんなことは考えずに、自分の未来が広がるよう自分自身の勉強を頑張るだけだもの。」
「勉強?」
「ええ、実は色々と勉強道具は持ってきているの。」
お嬢さんと思いきや、清佳さんはしっかりと自分の夢を持ち、向かっていくタイプの人なんだ。ちょっと尊敬。
「そうだ、芙美花さん、着物って洋服では合わせられないような大胆な色の組み合わせとかが出来ちゃうのよ。ほら、この帯を見て、沢山の色を使っているから、実は着物や小物とも合わせやすいの。」
清佳さんが来る前は会話が続くのか不安だったけど、気がつけば3時間くらい着物やら洋服の色合わせを二人で楽しんだ。
まるでセンスいいお姉さんが出来た感じ。
清佳さんが自分の夢を打ち明けてくれてよかった。