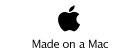作法教室
池ノ上静香(いけのうえしずか)様の場合
2週間が過ぎるのに、静香さんは誰ともあまり話をしない。どちらかというと、人を避けている感じ。勿論作法を習ったりテニスのときは、必要最小限程度話しているけど。だけど何かが引っかかる。
わたしも高校に入った当初は、なかなか周囲のお嬢さんたちと話せなかった。そりゃあ珠樹みたいなお嬢さんばっかりじゃあないけれど、何となく、何か漠然とした壁があったのを覚えている。
じゃあ静香さんは?
ちなみに静香さんは23歳で、大学院へ通っているとか。自己紹介の時に何かの研究をしていると教えてくれたけど、その名前すら覚えられていない。たぶんそこにいた全員の顔がクエスチョンマークを周りに散らしまくったんだと思う。だからお嬢様なのに、場の空気をちゃんと読んだ静香さんは、研究内容の説明まではしなかった。
もしくは…、穿った考え方をするならば、ワザと難しいことを言ってそれ以上興味を持たないようにしたんじゃないかと。今ならそんな考えも過ぎる。それくらい静香さんは誰とも話さない。かと言って、横柄とかそういうことでもない。
こんなことを思えるようになったのは、ここでの毎日に慣れてきたせいか不思議と何に対してなのかは分からない余裕が出てきたからだと思う。その余裕は更に、静香さんと話してみたいという好奇心まで後押しした。
だけど一緒に生活していても切欠ってなかなかない。
静香さんの前をさり気なく歩いて、ハンカチを落として拾ってもらう、っていうのもなぁ…。第一気付いてくれなかったら…、あ〜もう、どうしてそんな古いドラマのシーンみたいなのしかでてこないんだろ、この頭は。
—ドン—
「きゃ、」
「うわ、ごめんなさい。」
こんなことを考えて歩いていたら、思わず階段の踊り場で誰かにどっついてしまった。これまた古いドラマみたい。
でも、人間強く願えば叶う。
わたしの前には静香さん。
「ごめんなさい、考え事をしていて。」
「芙美花さんこそ大丈夫?わたしもちょっとボーっとしていて。」
偶然にもわたしがどっついたのは、静香さんだった。
「そうだ、静香さん、」
咄嗟に『そうだ』と言ってはみたものの、その先がでてこない。でもここは何とかしなくちゃ。
「あの、えっとぉ、その…、あ、っとぉ、ここにいるのにこんな質問可笑しいんですけど、大学について教えてもらえますか?」
「大学について?」
「はい、わたし進学予定なんで。その、静香さんは大学院に行ってるんですよね。ってことは、大学へも行っていたんですよね。だからその勉強を続ける為に、その先へ行ったってことですもんね。」
その質問に一瞬静香さんの表情が翳った気がしたけど、とにかくここは大学の話ということで畳み込んだ。
遠慮する静香さんに部屋に来てもらうのはすごく大変だった。
「そんなぁ、気にしないで下さい。お願いしているのはわたしですから。本当は現役の大学生がうちにいるんですけど、やっぱり兄弟だとかえって恥ずかしいから聞けないことがあって。」
「そうなの?」
「う〜ん、まあ。しかもうちは兄なんで余計適当にあしらわれそうというか、いつも間違えなくそうされているんで。」
「お兄様がいらっしゃるの?」
「ええ、まあ、使えない二人が。一番上はもう働いているんですけど、二番目は大学生なんです。」
心なしか、兄達の話に静香さんが興味を持ったような…。知り合い?な訳ないよねぇ。
部屋に入ってもらったのはいいけど、さてどうしよう。こういうときはお茶の用意、かな。
「静香さん、ちょっと待ってて下さいね。飲み物もらってきますから。」
「そんな、別に気を使わなくて大丈夫よ、芙美花さん。」
「いえいえ、ちょっと待ってて下さいね。」
だってこの時間は重要。大学って、何を聞けばいいのやら。
パントリーと呼ばれるところへ行くと今日も優しい飯塚さんがパウンドケーキと紅茶を快く用意してくれた。最近では飯塚さんとも仲良しで、紅茶の種類やらハーブティの種類なんかも教えてもらっている。
甘くて美味しいケーキと香高い紅茶は心をオープンにしてくれるよね、きっと。
「静香さん、もう知っているとは思うんですけど、わたし、ここには西園寺さんが考えていた本来の趣旨とは違って来ているんですよ。わたしとしては、これは今後役に立つかもしれない作法教室。西園寺さんに選ばれることはまずないとしても、それ以外にもお見合いとか結婚の予定は全くないんですよね。進学希望だし。で、夏休み明けには学部を絞らなきゃいけないんだけど、どうやって決めたらいいか分からなくて。」
「もう学部を決めるの?」
「あ、はい。付属の大学へそのまま行けるみたいなんで。」
「ああ、そういうことね。で、芙美花さんは成績的には選べる立場、ってことで合ってる?」
「はい、なんとか。わたし、珠樹さんと同じ高校なんですけど、バックグラウンドは全く違ってただの奨学生なんですよ。だから、成績は常に一定の所をキープし続けなきゃいけなかったから。」
「バックグラウンドなんか関係ないわ。もし、芙美花さんが努力しなかったらそもそも奨学生にだってなってなかったんだから。何よりも重要なのは、自分自身。そして、その自分が何を望んでいるか。」
静香さんの言葉はとても力強かった。普段はあまり話さないのが嘘のよう。
けれどその言葉をはなった直後、静香さんの目から涙が零れた。
「静香さん、あの、」
「あ、ごめんなさいね、芙美花さん。…ごめんなさい。」
「あ、いえ、わたし、何か、変なこととか言っちゃいました?」
「ううん、違うの。あの、ごめんなさい。まだ、全然大学の話をしてないけど、今日はごめんなさい。また、改めてでいいかしら?」
謝りながらも静香さんの目からは何故か涙が。さすがに引き止めることは出来なかった。