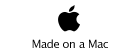作法教室
再び西園寺邦和様の場合
静香さんを除いて、朝の散歩時の会話が増えた。珠樹も話してみると悪い子じゃないし。ただ世間知らず(あ、この子は世間なんて知らなくてもいいのかもしれないけど。)というか、育った環境の違いというかで、どつきたくなるような事は良くあるけど。食事の後とかでも、みんな色々話すようになったし。そうそう、今思うと、最初の頃の会話って腹の探りあいって感じだったな。
で、邦和。こいつにはとびきりのセンサーが付いている。お嬢様たちがいるときは、なんていうの?、わたしには背筋も凍るような笑顔にしかみえないんだけど、それを浮かべながら会話をしている。で、そのセンサーにお嬢様が一人も引っかからなくなると、途端に笑顔は消えるし、言葉使いも変わる。
「芙美花、ちょっと話があるんだけど。今日の午後、駅近くのカフェに連れていってやるから付き合え。」
何故命令形?こいつのセンサーを通して見ると、わたしは召使か何かに映るのだろうか?
「やだ。」
「なんでだよ。うまいらしいぞ、ケーキ。」
そう言う問題じゃない。
「大森さんが作ってくれるのもすごくおいしいし。第一、邦和と出かけたって楽しくなさそう。」
「はぁ?、おまえ、俺に誘われたい子はたくさんいるんだぞ。傍にいれるだけでも光栄に思え。とにかく、午後の分が終わったら出かけるからな。」
断ったのに…、結局邦和と出かけなきゃいけないんだ。
だけど、誘われたい子って、そりゃあ勿論西園寺の名前か、あの顔、うっ、その先を言うと邦和の顔がいいことを認めてしまう。とにかく、せっかく軽井沢にいるんだから観光へ行くと思えばいいっか。
午後のお稽古が終わり、部屋に戻るとどうやら扉の下から差し込まれたらしい紙が。そこには本当に綺麗な字で『テニスコートの入り口に』と書かれていた。誰からのものかは言わずもがな、やつしかいない。
テニスコートへ行くと、入口付近のフェンスによりかかり下を向いている邦和が。その姿は邦和の二重人格振りを知らなければ、ドキっとしてしまうところだった。
わたしの足音、それとも気配?どっちかは分からないけど、それに気付いた邦和が顔を上げわたしを視界に留めると、何も言わずに歩きだした。その背中がわたしについて来いと言っているのは明白で…、だからこそ逆らいたくなる。
その場に突っ立ていると、足音が止まったことに気が付いたのか邦和が振り返った。
そして一言。
「来いよ。」
何かイヤじゃない?背中といい、言葉といい、それに従うの。
やっぱり突っ立ていたら、おまえは送り迎えが必要な幼稚園児かとブツブツ言われ、手を引かれた。
動く気がなかったから、引かれた拍子に思わず前につんのめると邦和が微かに笑った。きっとばかにされているのに、なぜか嫌じゃないって言うか、良かった。わたしってマゾ?って、えっ、手?
これってつないでる?やだ、手に全部の感覚が集中してるよ。
「あの、邦和、手、放して。ちゃんとついて行くから。」
「どうだか。」
そう言って、邦和は一度手をぎゅっと握った。
手が熱い。きっと汗ばんでいる。
握られている手が心臓みたいにドキドキしてきた。
邦和がわたしの手を放したのは、車の扉に手を伸ばしたときだった。二人で出かけるんだから、わたしが座るべきシートは確かにここになっちゃうよね。タクシーじゃないんだから、後ろに座るのも変だし。でも、扉を開けてくれるとは思わなかった。こういうところはちゃんと躾けられているんだ。あ、もしかして慣れ?本人の話からすると、ガールフレンドたくさんいるみたいだから。
車の中では何を言われるだろうかと構えていたんだけど、邦和は普通に最近の出来事や、大学での話をしてくれた。ただお店に着く直前におばあちゃんのことを聞いてきた。
「ところで芙美花は自分のばあさんがどういう人だったか知ってるのか?」
「ううん、全然。あ、出身は良いところのおうちだって知ってるけど、それ以外は。」
「そっか、」
邦和はそれ以上その話は続けなかった。でもなんでおばあちゃんのことを?昨日の静香さんの涙といい、邦和の質問といい不思議。